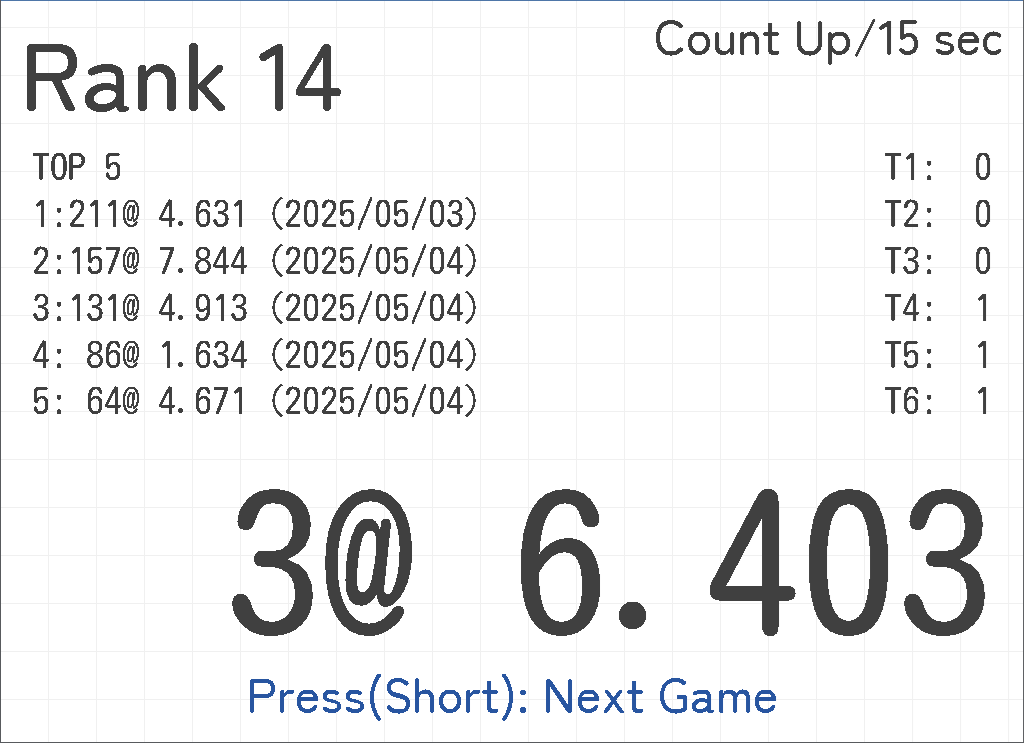2025年5月16日
フォントがおかしいので直した
目次: 自宅サーバー
このブログ、フォント設定が2つほどおかしかったので直しました。今まで見づらくてすみません。
1つ目は一部の環境(Linux向けChromeなど)からこのサイトを見るとサンセリフ体(ゴシック体)ではなくセリフ体(明朝体)で表示される現象を直しました。セリフ体になってしまう現象は以前から認識していて不思議だな?とは思ったものの、原因が良くわからず放置していました。
Developer toolsでCSSを確認していたら、font-family: sans-serif, serifと指定していた箇所がありました。原因も何も、自分で指定してただけだったのか……。こんな単純なことに10年以上気づいていなかった。
2つ目はmonospace系の文字が表示されるpreタグなどの文字が小さかったのを直しました。今までfont-size: smallerにしていたんですが、monospaceは元々少し小さいサイズで表示されるブラウザが多くて、めちゃくちゃ字が小さくなっていました。
しかもこちらの現象は認識していませんでした。自分のFirefox環境はmonospaceのフォントサイズを少し大き目に指定している&そのことを忘れており、デフォルト設定のブラウザで見ると字が小さすぎることに気付いてなかったです。すまねぇ。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
2025年5月14日
signalの未定義動作を見る - その2
目次: C言語とlibc
シグナルマスク(sigprocmaskのマニュアル)の「規定されていない」使い方をするとどうなるか?の続きです。5つのマルチスレッド(親スレッド+4つの子スレッド)で全員でsigwait()するのは共通で、誰がsigprocmask()を呼ぶか?を変えながら、下記4パターンを試します。
- 最初のスレッドがsigprocmask()
- 最初のスレッド「以外」の1スレッドがsigprocmask()
- 全スレッドがsigprocmask()
- 全スレッドがpthread_sigmask()
今回は結果3と4を紹介します。1〜3は定義されていない動作ですが、4は比較用に実施する「正しい方法」です。
結果3 - 全スレッドがsigprocmask()
全スレッドがsigprocmask()した場合です。ゆっくり5回シグナルを送ると、親スレッド(th 4)のsigwait()がシグナルを受け取り、子スレッド(th 0)のsigwait()はEINTRが返ります。
結果3 - シグナルが少ない場合
$ g++ -Wall -g -O2 -DUSE_SIGPROCMASK_ALL -DID_MAINTHREAD=1 signal_thread.cpp && ./a.out Use sigprocmask th 0: sub (child ) thread start th 0: sigprocmask(block) th 1: main (child ) thread start th 1: sigprocmask(block) th 2: sub (child ) thread start th 2: sigprocmask(block) th 4: sub (parent) thread start th 4: sigprocmask(block) th 3: sub (child ) thread start th 3: sigprocmask(block) th 3: loop start th 0: loop start th 2: loop start th 1: loop start th 4: loop start th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call)
良い感じです。また結果1(親スレッドがsigprocmask())と異なり、大量にシグナルを送りつけてもabortしないのも良いです。
結果3 - シグナルが多い場合
$ g++ -Wall -g -O2 -DUSE_SIGPROCMASK_ALL -DID_MAINTHREAD=1 signal_thread.cpp && ./a.out Use sigprocmask th 0: sub (child ) thread start th 0: sigprocmask(block) th 1: main (child ) thread start th 1: sigprocmask(block) th 2: sub (child ) thread start th 2: sigprocmask(block) th 4: sub (parent) thread start th 4: sigprocmask(block) th 3: sub (child ) thread start th 3: sigprocmask(block) th 3: loop start th 0: loop start th 2: loop start th 1: loop start th 4: loop start (...略...) th 2: sigwait failed (Interrupted system call) th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 0: got SIGUSR1 th 1: got SIGUSR1 th 2: got SIGUSR1 th 2: got SIGUSR1 th 1: sigwait failed (Interrupted system call) th 0: got SIGUSR1 th 4: sigwait failed (Interrupted system call) th 3: sigwait failed (Interrupted system call) th 2: sigwait failed (Interrupted system call) th 1: got SIGUSR1 (別ターミナルから) $ while :; do kill -USR1 123450; if [ $? -ne 0 ]; then break; fi; done
良さそうですね。
結果4 - 全スレッドがpthread_sigmask()
正しい方法(全スレッドがpthread_sigmask())はどんな動きでしょうか?結果だけ先に書いてしまうと、全スレッドがsigprocmask()したときと同じ動きをするようです。
結果4 - シグナルが少ない場合
$ g++ -Wall -g -O2 -DUSE_PTHREADSIGMASK -DID_MAINTHREAD=1 signal_thread.cpp && ./a.out Use pthread_sigmask th 0: sub (child ) thread start th 0: pthread_sigmask(block) th 1: main (child ) thread start th 1: pthread_sigmask(block) th 2: sub (child ) thread start th 2: pthread_sigmask(block) th 4: sub (parent) thread start th 4: pthread_sigmask(block) th 3: sub (child ) thread start th 3: pthread_sigmask(block) th 3: loop start th 2: loop start th 0: loop start th 1: loop start th 4: loop start th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call)
結果3(全員sigprocmask())と同じ動きをしています。当然ながら、大量にシグナルを送りつけてもabortしません。
結果4 - シグナルが多い場合
$ g++ -Wall -g -O2 -DUSE_PTHREADSIGMASK -DID_MAINTHREAD=1 signal_thread.cpp && ./a.out Use pthread_sigmask th 0: sub (child ) thread start th 0: pthread_sigmask(block) th 1: main (child ) thread start th 1: pthread_sigmask(block) th 2: sub (child ) thread start th 2: pthread_sigmask(block) th 4: sub (parent) thread start th 4: pthread_sigmask(block) th 3: sub (child ) thread start th 3: pthread_sigmask(block) th 3: loop start th 2: loop start th 0: loop start th 1: loop start th 4: loop start (...略...) th 2: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 1: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: sigwait failed (Interrupted system call) th 0: got SIGUSR1 th 4: got SIGUSR1 th 0: got SIGUSR1 th 3: sigwait failed (Interrupted system call) th 3: got SIGUSR1 th 2: sigwait failed (Interrupted system call) th 2: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 0: got SIGUSR1 th 1: sigwait failed (Interrupted system call) th 3: sigwait failed (Interrupted system call) th 3: got SIGUSR1 th 0: got SIGUSR1 th 4: sigwait failed (Interrupted system call) th 2: sigwait failed (Interrupted system call) th 1: sigwait failed (Interrupted system call) (別ターミナルから) $ while :; do kill -USR1 123450; if [ $? -ne 0 ]; then break; fi; done
4つの結果から推測するにpthread_sigmask()とsigprocmask()は同じシステムコールを使っているかもしれません。libcのソースコードを見ればわかるはずなので、また今度に見ようと思います。
ソースコード
こちらからどうぞ。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
2025年5月12日
signalの未定義動作を見る - その1
目次: C言語とlibc
シグナルマスクのマニュアル(sigprocmaskのマニュアル)を見ると下記のように「規定されていない」とあります。実際Linuxだとどうなるか気になります。
マルチスレッドのプロセスでsigprocmask()を使用した場合の動作は規定されていない。
実行環境は下記のとおりです。他のプラットフォームや過去/将来のバージョンのLinuxで今回の実験結果と同じ動作をするとは限りませんのでご注意ください。
- Debian Testing (trixie/sid)
- Linux 6.12.12-1
実験内容は5つのマルチスレッド(親スレッド+4つの子スレッド)で全員でsigwait()するのは共通、誰がsigprocmask()を呼ぶか?を変えながら、下記4パターンを試します。
- 最初のスレッドがsigprocmask()
- 最初のスレッド「以外」の1スレッドがsigprocmask()
- 全スレッドがsigprocmask()
- 全スレッドがpthread_sigmask()
最後のパターンはマルチスレッドでsigwait()する場合の正しい方法(全スレッドがpthread_sigmask())で、他の3つと動作を比較するためのものです。
プログラム
コードは長くなってしまったので最後にファイルへのリンクを張っておきます。
実験方法はコンパイル時にマクロを適宜切り替えて、生成された./a.outを起動し、別のターミナルからkillコマンドなどでSIGUSR1を送るだけです。
結果1 - 最初のスレッドがsigprocmask()
最初のスレッドがsigprocmask()した場合です。ゆっくり5回シグナルを送ると、親スレッド(th 4)のsigwait()がシグナルを受け取り、子スレッド(th 0)のsigwait()はEINTRが返ってきます。
結果1 - シグナルが少ない場合
$ g++ -Wall -g -O2 -DUSE_SIGPROCMASK -DID_MAINTHREAD=4 signal_thread.cpp && ./a.out Use sigprocmask th 0: sub (child ) thread start th 1: sub (child ) thread start th 2: sub (child ) thread start th 4: main (parent) thread start th 4: sigprocmask(block) th 3: sub (child ) thread start th 3: loop start th 2: loop start th 4: loop start th 0: loop start th 1: loop start th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call) th 4: got SIGUSR1 th 0: sigwait failed (Interrupted system call)
一見すると良い感じに動くように見えますが、大量にシグナルを送りつけるとabortします。ありゃりゃ。
結果1 - シグナルが多い場合
$ g++ -Wall -g -O2 -DUSE_SIGPROCMASK -DID_MAINTHREAD=4 signal_thread.cpp && ./a.out Use sigprocmask th 0: sub (child ) thread start th 1: sub (child ) thread start th 2: sub (child ) thread start th 4: main (parent) thread start th 4: sigprocmask(block) th 3: sub (child ) thread start th 3: loop start th 1: loop start th 0: loop start th 2: loop start th 4: loop start ユーザー定義シグナル1 (別ターミナルから) $ while :; do kill -USR1 123450; if [ $? -ne 0 ]; then break; fi; done
一見動くように見えて、だめなパターンですね。
結果2 - 最初のスレッド「以外」の1スレッドがsigprocmask()
最初のスレッド「以外」の1スレッドがsigprocmask()した場合です。1回シグナルを送っただけでabortしました。
結果2 - シグナルが少ない場合
$ g++ -Wall -g -O2 -DUSE_SIGPROCMASK -DID_MAINTHREAD=0 signal_thread.cpp && ./a.out Use sigprocmask th 0: main (child ) thread start th 0: sigprocmask(block) th 1: sub (child ) thread start th 2: sub (child ) thread start th 4: sub (parent) thread start th 3: sub (child ) thread start th 3: loop start th 0: loop start th 2: loop start th 1: loop start th 4: loop start ユーザー定義シグナル1
結果1の動きを見る限り納得の結果と言えるでしょう。シグナルは常に親スレッドにも飛んでいたので、シグナルをマスクしてない親スレッドはabortするのはそりゃそうだなと思います。
続きはまた今度やります。
ソースコード
こちらからどうぞ。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
2025年5月9日
JavaとM5Stamp C3とBluetooth LE - Bluetoothデバイスとの通信改善
目次: Arduino
M5Stamp C3 + Raspberry Piを組み合わせて作った的あてゲーム、秋葉原のTarget-1(お店のサイト)で壊れることなく1年ほど安定稼働しているようです。良かった良かった。しかし最近、故障ではないもののタイトル画面に戻ってしまう頻度が増えているそうです。
以前に日記で紹介したとおり、的あてゲームのシステムはM5Stamp C3をBluetooth LEデバイスにして、Linux PCもしくはRaspberry PiなどのLinux SBCと通信しています。Bluetoothの接続が切れるとタイトル画面に戻って再接続する実装にしていますので、不意にタイトル画面に戻る = Bluetoothの接続が切断されていることを意味します。
原因の仮説と対策
お店での運用を見ていると、ゲームリザルト画面で放置されることが多いです。今の実装ではリザルト画面でBluetoothの通信を一切行いません。あまりにも長い間通信しないとBluetooth接続が切れてしまう?のかもしれません。
とりあえず今回は小手先の対処として、リザルト画面でM5Stamp C3本体のLEDを点滅させる指令を送り続け、Bluetooth接続を維持するようにしました。家でテストしてみたところ1日以上放置しても接続を維持できています。
代償として消費電力が0.1Wくらい増えますが、何度もタイトル画面に戻されるよりはマシでしょう……。
目指すは先代の実績?
先代のTSS(ターゲットシューティングシステム、作者さんの紹介サイト)は5年位稼働していたらしい(すごい!)ので、追いつくにはあと4年ですか、長いな〜……。
4年後を考えてみると、Linux側のマシンROCK 3Cはほぼ確実にEOL(End Of Life、生産終了、販売終了)だと思います。Linux側のシステムはHW依存は少ないし、SWも枯れたやつが多いので、そのとき販売されているお買い得なARM SBCボード(Raspberry Pi 6とか7とか?ROCK 3C後継のボードとか)への乗り換えは容易だと思います。
困るのはM5Stamp C3ですね。EOLになると別ボードへのSW移植とドッキングするためのボード再設計が必要でしょう。M5Stampは安くて良いんですけど、世代ごとに形がガンガン変わって互換性ゼロなのが良くない点ですね。作り直すとしたら、今のM5Stamp C3の2枚使い設計はダサいので、I/Oピン数の多いボード1枚に改めると思います。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
2025年5月5日
timespecの操作関数
目次: C言語とlibc
POSIXには時間を表す構造体が2つあります。マイクロ秒単位のstruct timevalと、ナノ秒単位のstruct timespecです。struct timespecの方が後発なのか、比較的新しいAPIはstruct timespecを使う傾向にありますが、基本的には混在しています。
timevalとtimespec
struct timeval {
time_t tv_sec; /* 秒 */
suseconds_t tv_usec; /* マイクロ秒 */
};
struct timespec {
time_t tv_sec; /* 秒 */
long tv_nsec; /* ナノ秒 */
};
見てのとおり構造体ですから、足し算や引き算をするにも桁上がりを考える必要があって一苦労必要かと思いきや、POSIXはtimeradd/timersubなどのマクロを用意しており、struct timevalの加減算と比較などが比較的簡単に行えます。便利ですね。
ではstruct timespecにも同様にtimespecadd/timespecsubがあると思いますよね?ところが一部のlibc(BSD系やnewlib)以外は実装していません。なぜ……!?
timeraddのtimespec版
#define timespecadd(a, b, res) \
do { \
(res)->tv_sec = (a)->tv_sec + (b)->tv_sec; \
(res)->tv_nsec = (a)->tv_nsec + (b)->tv_nsec; \
if ((res)->tv_nsec >= 1000000000) { \
(res)->tv_sec++; \
(res)->tv_nsec -= 1000000000; \
} \
} while (0)
#define timespecsub(a, b, res) \
do { \
(res)->tv_sec = (a)->tv_sec - (b)->tv_sec; \
(res)->tv_nsec = (a)->tv_nsec - (b)->tv_nsec; \
if ((res)->tv_nsec < 0) { \
(res)->tv_sec--; \
(res)->tv_nsec += 1000000000; \
} \
} while (0)
#define timespecclear(tsp) ((tsp)->tv_sec = (tsp)->tv_nsec = 0)
#define timespecisset(tsp) ((tsp)->tv_sec || (tsp)->tv_nsec)
#define timespeccmp(a, b, cmp) \
(((a)->tv_sec == (b)->tv_sec) ? \
((a)->tv_nsec cmp (b)->tv_nsec) : \
((a)->tv_sec cmp (b)->tv_sec))
いつもstruct timespecを要求するAPIを使うたびにtimespecadd/timespecsubがなくて演算しづらさにイライラするので、コピペで使い回せるように実装例をメモしておきます。この程度なら誰が書いてもほとんど同じコードになると思いますが、気になる方のためにもし著作権が発生する場合はBSD 3条項ライセンス扱いでお願いします。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
| < | 2025 | > | ||||
| << | < | 05 | > | >> | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近のコメント20件
-
 25年11月28日
25年11月28日
hdkさん (12/04 08:10)
「あれ、停止直前くらいの時のトルクコンバー...」 -
 25年11月28日
25年11月28日
すずきさん (12/03 11:24)
「トルクコンバーターがいてエンブレは掛かり...」 -
 25年11月28日
25年11月28日
hdkさん (12/02 08:02)
「"停止直前に急にエンブレがほぼゼロになる...」 -
 25年10月6日
25年10月6日
すずきさん (10/10 13:14)
「ですね。ccはもはやコンパイラというより...」 -
 25年10月6日
25年10月6日
hdkさん (10/10 08:27)
「ただのHello, worldでも試して...」 -
 25年9月29日
25年9月29日
すずきさん (10/03 00:29)
「なんと、メタパッケージ入れてなかったです...」 -
 25年9月29日
25年9月29日
hdkさん (10/02 06:51)
「あれ、dkmsは自動ビルドされるのが便利...」 -
 20年8月24日
20年8月24日
すずきさん (08/30 22:06)
「ですね、自分も今はPulseAudioを...」 -
 20年8月24日
20年8月24日
hdkさん (08/29 09:32)
「ALSA懐かしい... PulseAud...」 -
 16年2月14日
16年2月14日
すずきさん (08/04 01:31)
「お役に立ったようでしたら幸いです。」 -
 16年2月14日
16年2月14日
enc28j60さん (08/03 17:40)
「ちょうど詰まっていたところです。\n非常...」 -
 25年7月20日
25年7月20日
すずきさん (07/30 00:10)
「ギクシャクするのは減速時の2速シフトダウ...」 -
 25年7月20日
25年7月20日
hdkさん (07/29 07:38)
「2速発進でギクシャクするんですか? 面白...」 -
 25年7月20日
25年7月20日
すずきさん (07/28 23:16)
「なるほど。レガシィB4のATはDレンジで...」 -
 25年7月20日
25年7月20日
hdkさん (07/28 21:28)
「MT車でも1速はギクシャクするので完全に...」 -
 25年7月20日
25年7月20日
すずきさん (07/28 00:44)
「何日か乗ってみて気づいたんですが、Dレン...」 -
 25年7月20日
25年7月20日
hdkさん (07/22 22:59)
「2速発進って雪道モードっぽさがありますが...」 -
 20年8月16日
20年8月16日
すずきさん (07/21 23:27)
「ありがとうございます。リアル志向が肌に合...」 -
 20年8月16日
20年8月16日
こここさん (07/21 12:19)
「個人的でも「正直な感想」と「おすすめのハ...」 -
 20年8月16日
20年8月16日
すずきさん (07/01 01:11)
「そうですね。残念ながら私には向いてなかっ...」
最近の記事3件
こんてんつ
 wiki
wiki Linux JM
Linux JM Java API
Java API過去の日記
 2002年
2002年 2003年
2003年 2004年
2004年 2005年
2005年 2006年
2006年 2007年
2007年 2008年
2008年 2009年
2009年 2010年
2010年 2011年
2011年 2012年
2012年 2013年
2013年 2014年
2014年 2015年
2015年 2016年
2016年 2017年
2017年 2018年
2018年 2019年
2019年 2020年
2020年 2021年
2021年 2022年
2022年 2023年
2023年 2024年
2024年 2025年
2025年 過去日記について
過去日記についてその他の情報
 アクセス統計
アクセス統計 サーバ一覧
サーバ一覧 サイトの情報
サイトの情報合計:
本日:
 ソースコード
ソースコード