2024年12月24日
サンタ宇宙へ(2024年)
目次: サンタ
去年(2023年12月24日の日記参照)と同様に、飛行機の位置をリアルタイムに表示するFlightradar24というサービス(サイトへのリンク)にてサンタが出現しました。クリスマス・イブの日にサンタが出現するのは毎年恒例のお約束演出です。私が見たときは南米付近を飛んでいました。
去年までのサンタは表示された対地速度とサンタの位置から計算した速度が全く違っていたので、今年もチェックしてみようと思います。対地速度の表示ですが、今年は従来と異なり速度が変動しています。私が見たときの表示は11,000kts程度(20,000km/h, マッハ16くらい)でした。メチャ速いです、ジェット機なんて目じゃありません。
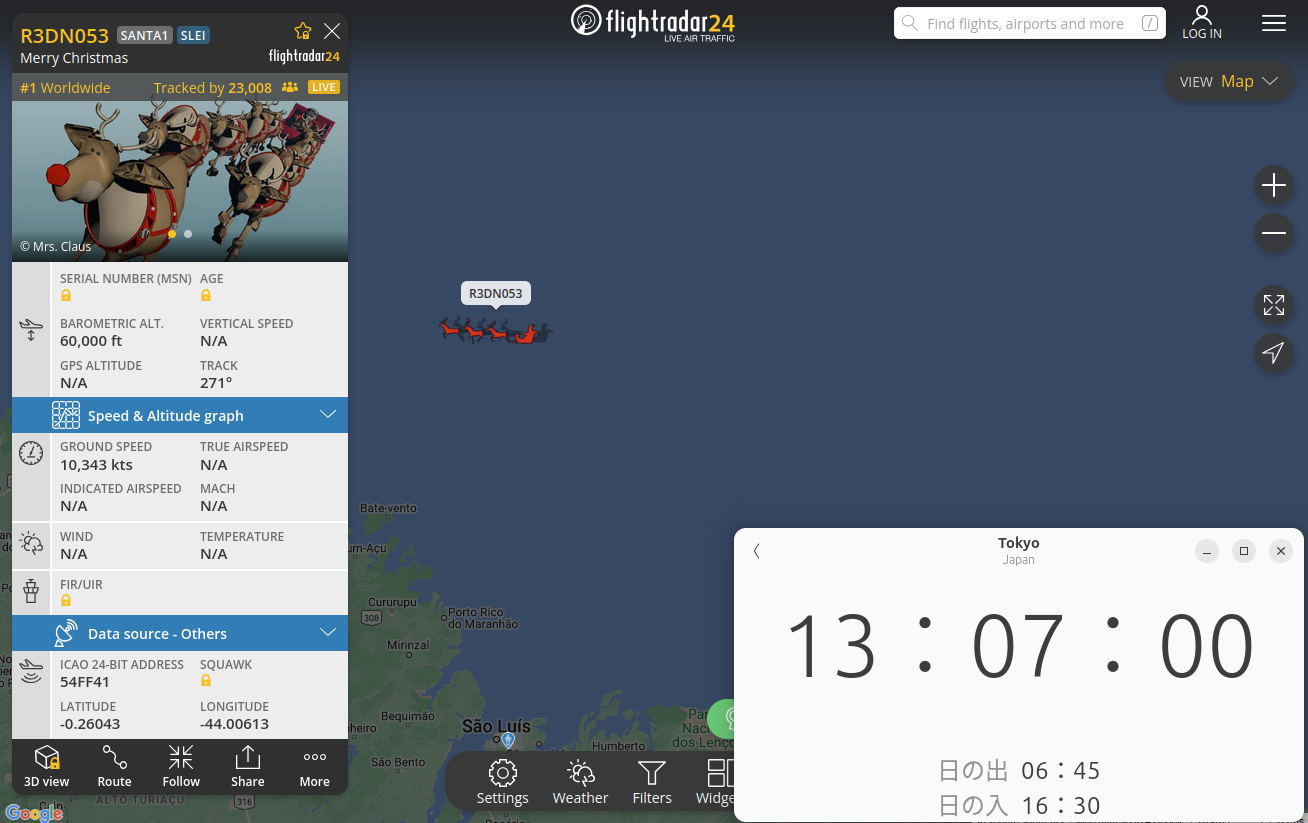
13:07:00時点の位置(緯度-0.26043度、経度-44.00613度)
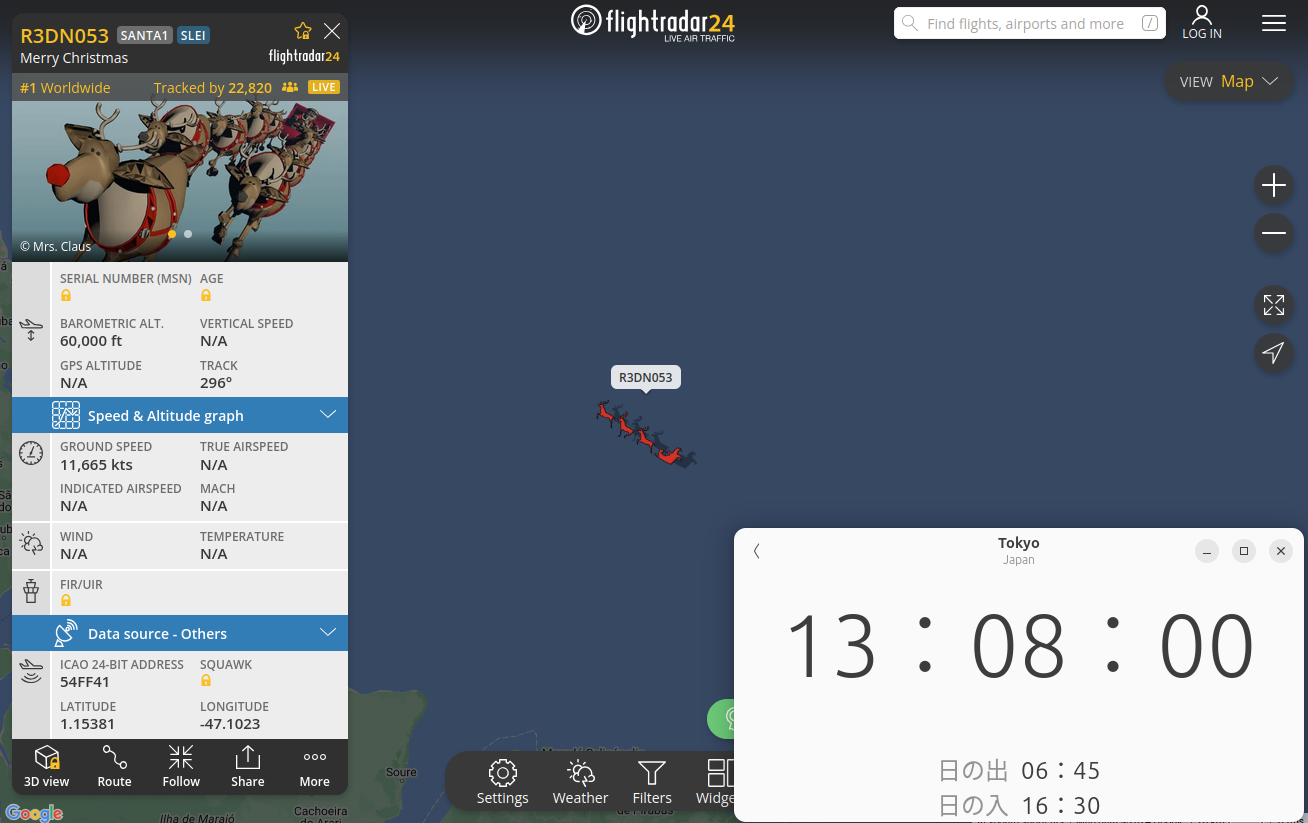
13:08:00時点の位置(緯度1.15381度、経度-47.1023度)
去年同様、ある程度の時間をあけ(今回は1分間)でどれくらい進んだか計算します。今回も距離の計算には国土地理院のページを使いました、緯度経度から距離を一発で計算してくれて便利です(サイトへのリンク)。
2地点間の距離は約378.5km、時間差は60秒から計算すると、対地速度は約22,710km/hです。地上でのマッハ18(ただし、サンタが飛んでいる高さ60,000ftsだとマッハ数はもっと高く出る)です。地球の重力と釣り合って人工衛星になれる速度(第一宇宙速度)が28,400km/hですから、今年のサンタさんは宇宙へ行かんばかりの勢いで疾走しています。
- 2021年: マッハ2
- 2022年: マッハ1.3
- 2023年: マッハ5
- 2024年: マッハ18
今年は例年と異なり表示速度と進んだ距離から計算した速度が大体合っていました。だんだん改善されているんでしょうか?来年の速度も気になりますので、覚えていたらまた計算してみましょう。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
2024年12月13日
nvJPEGとNVJPGとJetson APIその6 - Jetson Linux API JPEG encode編
目次: Linux
半年経ったら完全に忘れるのでメモします。最近JPEGのデコードエンコードが必要になって色々調べていました。Jetson特有のAPI群がありまして、API名はJetson Linux API(のなかのMultimedia APIs)だそうです(Jetson Linux APIドキュメント)。ハードウェアJPEGデコーダ/エンコーダ(NVJPG)を自動的に使用してくれます。
Jetson JPEG encoding
今回はエンコードのAPIをご紹介します。APIの使い方は簡単です。こんな感じでした。
Jetson Linux API JPEG encode API呼び出し順
NvJPEGEncoder *jpgenc = nullptr;
NvBuffer *inbuf = nullptr;
uint8_t *buffer = nullptr;
size_t bufsize = 0;
int r;
// Create
jpgenc = NvJPEGEncoder::createJPEGEncoder("jpgenc");
// Align
#define ALIGN_2N(a, b) (((a) + (b) - 1) & ~((b) - 1))
NvBuffer::NvBufferPlaneFormat fmts[3];
fmts[0].width = width;
fmts[0].height = height;
fmts[0].bytesperpixel = 1;
fmts[0].stride = ALIGN_2N(width, 256);
fmts[0].sizeimage = fmts[0].stride * fmts[0].height;
fmts[1].width = width / 2;
fmts[1].height = height / 2;
fmts[1].bytesperpixel = 1;
fmts[1].stride = ALIGN_2N(width / 2, 256);
fmts[1].sizeimage = fmts[1].stride * fmts[1].height;
fmts[2].width = width / 2;
fmts[2].height = height / 2;
fmts[2].bytesperpixel = 1;
fmts[2].stride = ALIGN_2N(width / 2, 256);
fmts[2].sizeimage = fmts[2].stride * fmts[2].height;
inbuf = new NvBuffer(V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE, V4L2_MEMORY_USERPTR, 3, fmts, 0);
if (!inbuf) {
printf("error in %s:%d\n", __func__, __LINE__);
return -1;
}
r = inbuf->allocateMemory();
if (r) {
printf("error in %s:%d\n", __func__, __LINE__);
return -1;
}
bufsize = width * height * 3 / 2;
buffer = (uint8_t *)malloc(bufsize);
// Encoding
uint8_t *jpegbuf = buffer;
size_t jpegsize = bufsize;
int quality = 80;
r = jpgenc->encodeFromBuffer(*inbuf, JCS_YCbCr, &jpegbuf, jpegsize, quality);
// Destroy
free(buffer);
delete inbuf;
delete jpgenc;
若干NvBufferの確保がややこしいです(参考: NvBufferPlaneのドキュメント、その隣のNvBufferPlaneFormatも参考になります)けど、基本的にはencodeFromBuffer()を呼ぶだけです。
実行
ソースコードを置いておきます。
使い方はコードの先頭にコメントで書いている通りですが、ここでも説明しておきます。引数はありません。ファイル名test_420.yuvのRaw YUV420ファイルを読み込んで、ファイル名jetson_420.jpgのJPEGファイルを書き出します。
コンパイル、結果確認
$ g++ -g -O2 -g -Wall \
-I jetson_multimedia_api/include/ \
-I jetson_multimedia_api/include/libjpeg-8b/ \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvJpegDecoder.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvJpegEncoder.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvBuffer.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvElement.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvElementProfiler.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvLogging.cpp \
jetson_enc.cpp \
-L /usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia/ \
-lnvjpeg
$ ./a.out
$ ffplay -i jetson_420.jpg
エンコード結果はJPEGです。ffplayでも普段お使いの画像ビューアでも、何を使って確認しても構いません。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
2024年12月11日
nvJPEGとNVJPGとJetson APIその5 - Jetson Linux API JPEG decode編
目次: Linux
半年経ったら完全に忘れるのでメモします。最近JPEGのデコードエンコードが必要になって色々調べていました。Jetson特有のAPI群がありまして、API名はJetson Linux API(のなかのMultimedia APIs)だそうです(Jetson Linux APIドキュメント)。ハードウェアJPEGデコーダ/エンコーダ(NVJPG)を自動的に使用してくれます。
Jetson JPEG decoding
今回はデコードのAPIをご紹介します。APIの使い方は簡単でこんな感じでした。
Jetson Linux API JPEG decode API呼び出し順
NvJPEGDecoder *jpgdec = nullptr;
NvBuffer *outbuf = nullptr;
int r;
// Create
jpgdec = NvJPEGDecoder::createJPEGDecoder("jpgdec");
// Decoding
uint32_t jpeg_pixfmt;
uint32_t jpeg_width;
uint32_t jpeg_height;
r = jpgdec->decodeToBuffer(&outbuf, jpegbuf, jpegsize, &jpeg_pixfmt, &jpeg_width, &jpeg_height);
// Destroy
delete outbuf;
delete jpgdec;
注意すべき点は2つあります。1つ目はdecodeToBuffer()が勝手にoutbufを確保して返してくるので、delete outbufしなければならないことです。Turbo JPEGと異なり、予めバッファを確保しておけばメモリ確保処理を回避するような仕組みはなさそうでした。イマイチです。
2つ目はProgressive JPEGがデコードできないことです。デコードしようとするとdecodeToBuffer()でハングします。どんなJPEGファイルが来るかわからない状況で使う場合、JPEGファイルの中身をチェックしてBaseline JPEGはハードウェアデコード、Progressive JPEGはソフトウェアデコードする仕組みが必要です。
しかし前に話したとおりJetson APIの裏にいるlibnvjpeg.soが謎にIJG JPEGのAPIを実装しているため、本家IJG JPEGのlibjpeg.soがリンクできません。この状態でどうやってProgressive JPEGをソフトウェアデコードすれば良いのでしょう。Jetson APIの裏にいるlibnvjpeg.soをIJG JPEGだと思って呼べば動作するんでしょうか?
実行
ソースコードを置いておきます。
使い方はコードの先頭にコメントで書いている通りですが、ここでも説明しておきます。引数はありません。ファイル名test_420.yuvのRaw YUV420ファイルを読み込んで、ファイル名jetson_420.jpgのJPEGファイルを書き出します。
コンパイル、結果確認
$ g++ -g -O2 -g -Wall \
-I jetson_multimedia_api/include/ \
-I jetson_multimedia_api/include/libjpeg-8b/ \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvJpegDecoder.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvJpegEncoder.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvBuffer.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvElement.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvElementProfiler.cpp \
jetson_multimedia_api/samples/common/classes/NvLogging.cpp \
jetson_dec.cpp \
-L /usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia/ \
-lnvjpeg
$ ./a.out
$ ffplay -f rawvideo -video_size 1920x1440 -pixel_format yuv420p -i jetson_420.yuv
デコード結果のRawvideoを確認するときはffplayを使うと便利です。
コメント一覧
- コメントはありません。
 この記事にコメントする
この記事にコメントする
| < | 2024 | > | ||||
| << | < | 12 | > | >> | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
こんてんつ
 wiki
wiki Linux JM
Linux JM Java API
Java API過去の日記
 2002年
2002年 2003年
2003年 2004年
2004年 2005年
2005年 2006年
2006年 2007年
2007年 2008年
2008年 2009年
2009年 2010年
2010年 2011年
2011年 2012年
2012年 2013年
2013年 2014年
2014年 2015年
2015年 2016年
2016年 2017年
2017年 2018年
2018年 2019年
2019年 2020年
2020年 2021年
2021年 2022年
2022年 2023年
2023年 2024年
2024年 2025年
2025年 2026年
2026年 過去日記について
過去日記についてその他の情報
 アクセス統計
アクセス統計 サーバ一覧
サーバ一覧 サイトの情報
サイトの情報合計:
本日:
 未来から過去へ表示(*)
未来から過去へ表示(*) 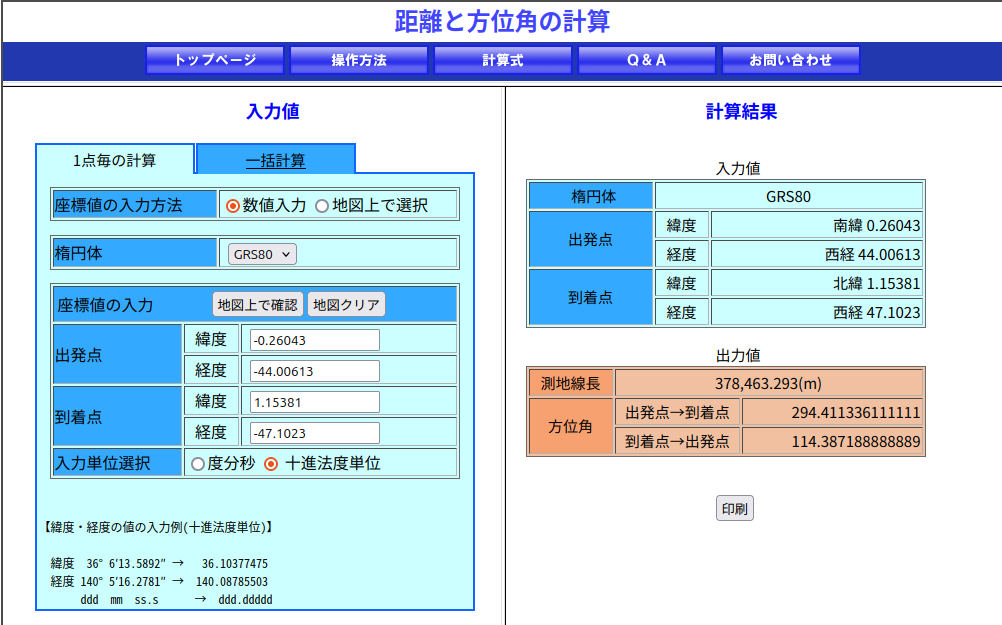
 Jetson Linux API JPEG encoding
Jetson Linux API JPEG encoding
